
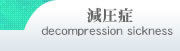
| 治療 | ||||||||||||||||||||
| 高気圧酸素治療とは | ||||||||||||||||||||
| 100%酸素を圧力の高い部屋(高気圧治療装置)で吸う治療を「高気圧酸素治療または再圧治療」といいます。高気圧酸素治療は、酸素をたくさん身体内に送り込むことによって、酸素不足またはダメージを受けている組織を回復させる治療です。 学会や厚生労働省の基準では、2絶対気圧(大気圧の2倍、水深10mの圧力)で1時間以上100%酸素を呼吸することを高気圧酸素治療と定めています。 私たちの身体では、赤血球中(動脈中)のヘモグロビンの95%以上が酸素と結びついています。ヘモグロビンと結びついている酸素を「結合型酸素」といいます。たとえば、病院などで100%の酸素を吸うと、ヘモグロビンがほぼ100%、酸素と結び付きます。さらに、高気圧酸素治療では、高気圧下で酸素を吸うため、圧力に応じて身体内に酸素が溶け込みます。血清(赤血球や白血球が浮いている血液の水分)に溶け込むわけです。これを「溶解型酸素」といいます。高気圧酸素治療では、特にこの「溶解型酸素」が威力を発揮します。治療圧力を高くすれば高くするほど、この「溶解型酸素」は増加しますが、過剰に入りすぎると副作用を現すことがあるため、病気や病状に合わせて圧力(治療表)を選択します。 |
||||||||||||||||||||
| 減圧症に対する高気圧酸素治療(再圧治療) | ||||||||||||||||||||
| 高気圧酸素治療には窒素気泡を再溶解させる作用と、身体から窒素を排泄させる作用(脱窒素作用)、虚血部への酸素供給作用があります。レジャーダイバーの減圧症では中枢神経系に気泡ができていることがほとんどなので比較的治療時間の長いアメリカ海軍治療表Table 6(図1) を使用することが望ましいと考えます(Table 6は空気で加圧するタイプの治療装置でなければ施行できない)。高気圧酸素治療を受けるまでに時間を要するときは応急的に酸素吸入を行います。脱窒素を目的とするため、酸素は15リットル/分以上の大流量が効果的です。重症かつ急性期には循環改善を目的として点滴補液も行います。グルコース(デキストロース)は浮腫を悪化させるため使用しないほうがよいでしょう。心肺停止状態にある者は、身体内気泡を取り除かなければ循環が回復しないため、高気圧酸素治療装置内で蘇生を行う必要があります(処置者が入ることのできる2種装置でなければ無理)。中枢神経障害の程度が軽度であっても、放置すると自覚症状が長引くことが多いため高気圧酸素治療を適応します。 |
||||||||||||||||||||
| 高気圧酸素の治療効果 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ● 高気圧酸素治療の副作用 | ||||||||||||||||||||
| 主に気圧外傷と酸素中毒があります。 気圧外傷は、ダイビング中に起こる耳のスクイーズやリバースブロックと同じものです。酸素中毒は、テクニカルダイビングやナイトロクッスダイビング(エンリッチドエアーダイビング)などで問題になるものと同じです。 酸素中毒には脳の症状(急性酸素中毒)と肺の症状(慢性酸素中毒)があります。急性酸素中毒の症状は、酸素を吸入している最中の、めまい、視野狭窄、まぶたや唇のぴくつき、吐き気、頭痛などです。高気圧酸素吸入中に発生した急性酸素中毒は、酸素マスクを外せば、通常5〜10分経たないうちに症状が消失します。症状が消失すれば、再びマスクを着用して治療を続行します。慢性酸素中毒の症状は呼吸器症状です。息切れ、胸の圧迫感、胸痛などを生じます。たとえば、Table6の場合、2日連続しても慢性酸素中毒はほとんど起きませんが、3日間連続すると約30%の方に何らかの症状が出現し、4日間連続して行うと約80%の方に副作用が生じます。 |
||||||||||||||||||||
| 治療表(治療テーブル)について | ||||||||||||||||||||
| 減圧症でもっとも使用される頻度が高い治療表は、米国海軍のTable 6です。Table 6の治療は、最高気圧2.8絶対気圧(0.28MPa)で、治療時間は約5時間です(PDF)。米国海軍のプロトコールでは、2.8絶対気圧に滞在し、症状が消失するか否かで治療表を選択することとしていますが、実際の臨床現場では、数名の患者様を同時に治療することもあるため、治療表の選択は、通常、加圧前に決定します。多くの減圧症に対してTable 6は有効ですが、中枢神経症状(知覚障害、運動障害、自律神経障害)、内耳症状、呼吸器症状がないケースの場合、すなわち四肢の運動器のみに気泡ができ症状が出現しているケース(いわゆるI型減圧症)または皮膚症状のみの減圧症についてはTable 5(約2時間半)を採用しても充分な効果が得られます。ただ、減圧症の神経症状は、脊髄分節に合致しないスポット的な知覚障害や、ある筋肉だけに限局した筋力低下など、非常に見逃されやすい神経障害を伴うため、問診や簡単な神経チェックだけからI型減圧症と診断するのは危険です。また、膀胱直腸障害などの重症な神経障害がある症例や、高気圧酸素治療中に症状が改善しにくい場合は、Table 6における「2.8絶対気圧下の20分酸素吸入5分空気呼吸」を1クールまたは2クール追加をすることもあり、さらに1.9絶対気圧に減圧した後に、重症な症状が残存しているときは、「1.9絶対気圧下における60分酸素吸入15分空気呼吸」についても1クール追加することがあります。ただし、酸素吸入時間が長ければ長いほど、または吸入時の圧力が高ければ高いほど、急性酸素中毒(脳症状)の副作用は起こりやすくなるので注意が必要です。また、Table 6は連日使用すると慢性酸素中毒(肺症状)の発生率は高くなります。重篤な場合を除いて、1日または2日おきに治療することが安全です。連日行う場合には少なくとも2回までとし、3日以上連日で治療したい場合は、治療時間の短い治療表を間に挿入するほうが安全です。なお、潜水した深度や時間については治療表には反映されません。 一方、動脈ガス塞栓症が強く疑われる場合は、まず「6.0絶対気圧下に30分間(空気呼吸)保圧」した後に減圧して、そのままTable 6に移行するという治療表(Table 6A)(PDF)が有用です。 たとえば、減圧症に対して通常の高気圧酸素治療(2.0絶対気圧、約1時間の治療)が効果を発揮しないわけではありませんが、重症な中枢神経症状を伴うダイバーでは充分な回復を期待できません。医療施設の経済状況からすればTable 6の治療は採算の合わない(赤字)治療であり、また、高気圧酸素治療装置は、日常、他の疾患のために稼動させていることが多く、減圧症のためだけに長時間割くことが困難な状況もあります。高気圧酸素治療を希望されるときは、前もって医療施設に問い合わせたうえで受診されることをお勧めします。 |
||||||||||||||||||||
| Table 6:治療時間|Table 6A:治療表 |
||||||||||||||||||||
※1スポーツ外傷に対して効果がある理由 |
||||||||||||||||||||
| 減圧症発症後、高気圧酸素治療を受けるまでの応急手当 | ||||||||||||||||||||
| 高気圧酸素治療を受けるまでに時間を要するときは酸素吸入を行います。脱窒素を目的とするため、酸素は15リットル/分以上の大流量が効果的です。 水分を多めに摂取することも大切です。
|
||||||||||||||||||||
| 減圧症発症後、受診まで控えること | ||||||||||||||||||||
| ■ ダイビング ■ 高所移動 ■ 航空機搭乗 ■ 激しい運動 ■ 疲労 ■ 脱水 ■ 症状のある部位を過度に動かす ■ 暑いお風呂またはサウナに長い時間入る ■ マッサージをする ■ アルコール(お酒)を飲む ■ 喫煙 ■ 高気圧エアーチェンバーなどの民間の空気加圧施術を受ける |
||||||||||||||||||||
| 高気圧酸素治療以外の治療 | ||||||||||||||||||||
| 急性期の重症減圧症には循環改善を目的として点滴補液を行います。グルコース(デキストロース)は浮腫を悪化させるため使用しないほうがよいとされています。心肺停止状態にある者は、身体内気泡を取り除かなければ循環が回復しないため、高気圧酸素治療装置内で蘇生を行う必要があります(処置者が入ることのできる第2種装置でなければ無理)。中枢神経障害の程度が軽度であっても、放置すると自覚症状を長期訴えることがあるため高気圧酸素治療を適応します。 |
||||||||||||||||||||
| 減圧症治療中&治療後の注意点 | ||||||||||||||||||||
| 治療に関して | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
予後